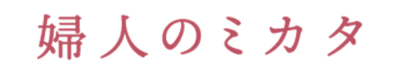更年期症状の救世主?大豆イソフラボンの真実とその効能

更年期に差し掛かるときに身体に現れる様々な不調。
食生活を気を付けたいと思っても、忙しい日々の中では、ついつい栄養が偏りがちになってしまいますよね。
そんな中でも特に意識的に食事の中で摂取したい成分として、大豆イソフラボンが挙げられます。
この成分がどうして更年期の女性にとって重要なのか、その真実と効能をわかりやすく解説します。
大豆イソフラボンとは?その驚くべき作用
大豆イソフラボンとは大豆に含まれる化合物で、女性ホルモンに似た働きをすることで知られています。
更年期になると女性ホルモンのエストロゲンが減少しますが、大豆イソフラボンはその役割を補ってくれるのです。
大豆イソフラボンは文字通り大豆製品などに多く含まれています。
<食事に取り入れたい大豆食品とは>
- 豆腐
- 納豆
- 豆乳
- 油揚げ
上記のような食材を毎日の食事で意識的に摂取することで、更年期症状の改善が期待できると言われています。
更年期症状と大豆イソフラボンの関係
更年期は、閉経前後5年ずつの期間を指し、一般的には45歳~55歳前後のことが多いです。
更年期は体内のエストロゲン(女性ホルモン)の分泌が減少し、それにより体や心に様々な不調が出現します。
この不調を「更年期症状」と呼び、更年期症状を抱える人の中で特に重い症状が現れる場合を更年期障害と言います。
更年期は全女性に訪れ、全女性の約6割に何かしらの更年期症状が発生します。
突然のほてりや頭痛、倦怠感、不眠といった身体的な症状に加え、落ち込みや不安、そして「いらいら」といった精神的な症状もあるため、更年期症状の具体的な症状は人により様々です。
大豆イソフラボンはエストロゲンに似た作用のあるエクオールのもととなるため、更年期症状を和らげる効果が期待できます。
大豆イソフラボンの効能:骨や肌にも良い?
大豆イソフラボンの効能は、更年期症状の緩和だけではありません。
<大豆イソフラボンに期待される効果>
- 骨粗しょう症の予防
- コレステロールの調整
- 肌の健康維持
例として、カルシウム不足による骨の弱化が更年期女性によく見られる問題ですが、大豆イソフラボンはこの問題も補ってくれます。
そのため、毎日の食事で取り入れることが一石二鳥の効果があると言われています。
大豆イソフラボンの摂取方法と漢方薬
大豆イソフラボンを効果的に摂取するためには、豆腐や納豆、豆乳などの大豆製品を毎日の食事に取り入れるとよいでしょう。
しかし、なかなか毎日の食生活で摂取するのが難しいといった人には、大豆イソフラボンを含む漢方薬によって摂取するといった方法もあるでしょう。
「当帰芍薬散」などの漢方薬は、ホルモンバランスを整えることで更年期の不調を和らげる効果が期待されています。
過剰摂取の注意!バランスが大切
上記で大豆イソフラボンの良い効果を伝えてきましたが、摂取にあたっては、一日にとるべき適正量があり、それを守る必要があります。
過剰に摂取した場合、吐き気や頭痛など体調に異常をきたすこともあるため、バランスの取れた食事から適正な量を摂るように心がけましょう。
具体的には、1日に40-70mgの範囲での摂取が推奨されています。必要であれば、栄養士や専門の医師に相談してみるのも良いでしょう。
まとめ
更年期症状の症状は多岐に渡りますが、適切な理解と対策により、その症状は改善可能です。
自分一人で悩まずに、医師との相談や情報収集を通じて、自分に合った方法を見つけ乗り越えていきましょう。