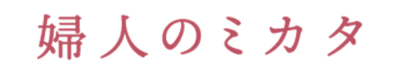更年期は最も骨密度が下がる時期?骨粗しょう症と更年期障害の深い関連性

更年期の女性が直面する課題の一つ、骨粗しょう症。
それは、更年期障害とどのような関連性があるのでしょうか?
今回は、その深いつながりを詳しく解説します。
早期発見と予防方法も伝授しますので、安心な更年期を迎えるための知識としてぜひご利用ください。
更年期障害とは?
更年期は、閉経前後5年ずつの期間を指し、一般的には45歳~55歳前後のことが多いです。
更年期は体内のエストロゲン(女性ホルモン)の分泌が減少し、それにより体や心に様々な不調が出現します。
この不調を「更年期症状」と呼び、更年期症状を抱える人の中で特に重い症状が現れる場合を更年期障害と言います。
更年期は全女性に訪れ、全女性の約6割に何かしらの更年期症状が発生します。
突然のほてりや頭痛、倦怠感、不眠といった身体的な症状に加え、落ち込みや不安、そして「いらいら」といった精神的な症状もあるため、更年期症状の具体的な症状は人により様々です。
更年期と骨密度の関係
閉経前後に女性ホルモン(エストロゲン)分泌が減少すると、それに伴い骨密度が低くなります。
これは、エストロゲンが古い骨を新しい骨に生まれ変わらせるサイクルを手助けしているからです。
エストロゲンが減る更年期は、このサイクルが上手くまわらなくなってしまうことがあります。
最も骨密度が低下するのは、閉経後最初の2年間と言われています。
骨粗しょう症の症状
骨粗しょう症は、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。
発症した場合、転倒などのちょっとした衝撃でも骨折する可能性があります。
初期の段階では症状がほとんど現れませんが、進行すると腰痛や背中の痛み、背が丸くなるなどの症状が出ることがあります。
骨粗しょう症の早期発見
骨粗しょう症によって骨が最も擦り減ってしまいやすい箇所は、顔、特に下あごと言われています。
「最近頬がたるんできた」と思ったら注意してください。
骨粗しょう症は早期に発見することが大切です。
定期的な健康診断で骨密度を測定することで、自身の骨の状態を把握できます。
自治体が行う骨粗しょう健診で年に一度程度骨密度を調べて見てください。
20歳と44歳の骨密度を基準として、20~30%減少を骨量減少、39%以上を骨粗しょう症と診断します。
更年期障害と骨粗しょう症の予防方法
骨を守るためには、適度な運動とバランスの良い食事が重要です。
特にカルシウムと、カルシウムの吸収・定着を助けるビタミンD・ビタミンKを摂るようにしてください。
<カルシウム>
歯や骨の重要な構成要素です。
カルシウムが不足していると、骨の成長が促進されず、体に様々な症状がでやすくなります。
食材:大豆食品、乳製品、ごま、小松菜、チンゲン菜、干しエビ、ワカサギなど
<ビタミンD>
カルシウムやリンの吸収を促し、骨を丈夫にします。
免疫や認知機能を調整する役割もあります。
食材:鮭、うなぎ、さば、卵など
<ビタミンK>
ビタミンDと共にとることで、骨密度を高め、骨粗しょう症を防ぐ効果を有します。
食材:ブロッコリー、小松菜、モロヘイヤ、納豆、海藻など
また、骨に重すぎない適度な負担をかける運動(ウォーキング、軽いジョギング、縄跳び)等を習慣化しましょう。
漢方薬による対策
更年期による骨粗しょう症に対しては、漢方薬の服用も有効な対策な一つです。
“”補中益気湯””や””加味逍遙散””などの漢方は更年期症状の緩和を助け、ひいては骨の健康を維持するのにも役立つ有効です。
ただし、漢方薬は個々の体質や症状により効果が異なるため、専門の医師の診察を受け適切な薬を服用することを推奨します。
まとめ
以上のことから、更年期の健康管理は、日々の生活習慣の見直しや漢方薬の服用による対策、定期的な健康チェックが骨粗しょう症への対策として重要であることが分かります。
自身の体を大切にし、健やかな更年期を過ごすために、身近にあるできることから始めてみてください。